取るなら活かす、活かせないなら取らない データ時代の“ユーザーファースト”
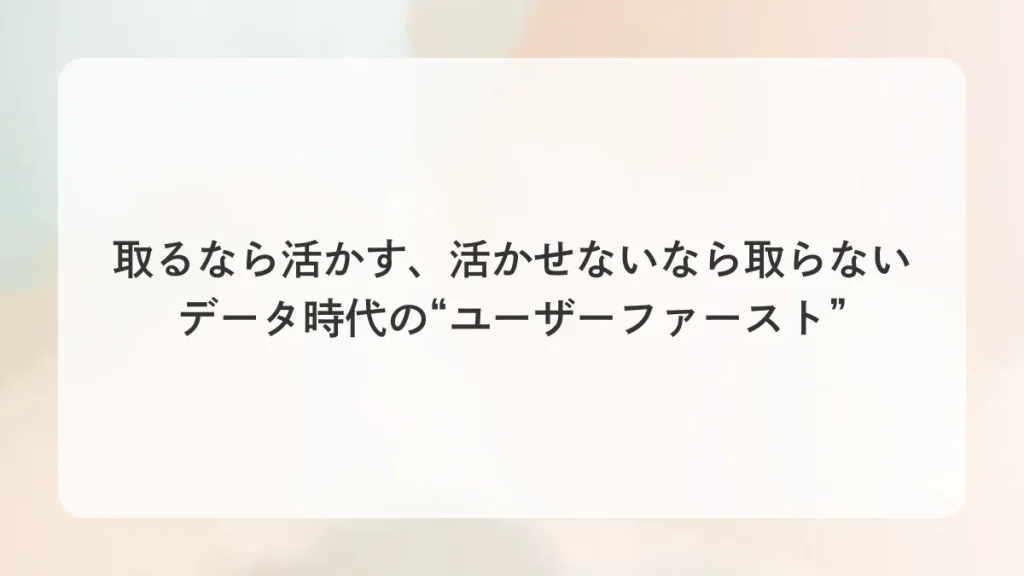
データを取ることが目的になっていないか?
外部からサイト改善や分析に関わる中で、何度も出会ってきた違和感があります。
それは、「データは揃っているのに、体験の話がどこにも出てこない」という状況です。
多くの企業が「データドリブン」を掲げるようになりました。アクセス解析、ヒートマップ、CRM、MAツール、BIダッシュボード……。情報はどんどん可視化され、あらゆる指標がリアルタイムで確認できる時代です。
しかし、実際の会議や改善の場で語られるのは、PVやCVR、離脱率といった数値の話ばかりで、
- 「そのときユーザーは何を期待していたのか」
- 「なぜその行動を取ったのか」
といった体験の文脈が、いつの間にか議論の外に置かれている場面をよく見かけます。
PV、CVR、離脱率、クリック率──。確かにどれも重要な指標です。
ただ、それを“どう活かしているか”が曖昧なまま、数値を追うこと自体が目的化してしまっているケースも少なくありません。
「とりあえず計測しておこう」から始まったタグ設置が、1年後には誰も見ないレポートを量産している。
データを取ること自体が、安心材料やアリバイになってしまっている現場も少なくないのです。
この記事でわかること
- データを取る目的が重要であり、データ活用が重要
- データ活用において、ユーザーの体験や期待を考慮することが必要
- 数値だけでなく、ユーザーの行動理由や感情を理解する必要性
- データは結論ではなく問いを立てるための材料
- データを取ることは手段であり、ユーザー理解が目的
- データ活用は数値を動かすことではなく、人の行動や気持ちを理解し、体験に反映すること
「ユーザーファースト」を名乗るマーケティングの落とし穴
「ユーザーファースト」という言葉は、今やどの企業も掲げています。でも、その実態を見てみると、ユーザーよりも“数値”を優先した意思決定が行われていることが少なくありません。
例えば、CVRを上げるためにフォーム項目を削減したり、クリック率を上げるためにバナーを増やしたりする施策。一見、ユーザーの行動を最適化しているように見えますが、実際には「数字が動いたかどうか」ばかりに焦点が当たってしまうのです。
データを根拠にした判断は合理的に見えますが、その裏で「なぜその行動をしたのか」「どんな感情で離脱したのか」といった“人の文脈”が抜け落ちてしまう危険があります。人の気持ちはグラフでは表せません。にもかかわらず、企業は数値だけをもって「改善された」と判断してしまうことがあるのです。
こうした状況では、ユーザー理解よりもKPI達成が優先され、結果的に体験の質が犠牲になってしまいます。つまり、“ユーザーファースト”を掲げながら、実際には“データファースト”になっているという矛盾が起きているのです。
データを「どう使うか」で体験は変わる
データが悪いわけではありません。問題は、その“使い方”です。たとえば、ユーザーの離脱率が高いページを見つけたとき、「デザインが悪い」と決めつけて改修を進めてしまうケースがあります。しかし、実際にはコンテンツ内容がユーザーの期待とズレているだけかもしれません。
数字は「結果」を示してくれますが、「理由」までは教えてくれません。だからこそ、数値を見たあとに「なぜ?」を繰り返し問い直す姿勢が必要です。
- なぜこのページで離脱が多いのか?
- なぜこの導線ではクリックされないのか?
- なぜこのキャンペーンは反応が低いのか?
この「なぜ」を丁寧に掘り下げることで、データが“理解”に変わっていきます。データを「判断の材料」にとどめるのではなく、「対話の起点」として使うことが、真にユーザーを理解するための第一歩ではないでしょうか。
数字の裏にある“行動の理由”
アクセス解析で示されるのは、あくまで「行動の結果」です。そこに至るまでの思考や感情、環境はデータには残りません。たとえば「3秒で離脱」したユーザーがいたとして、その理由はページの読み込みが遅かったのか、他のサイトで答えを見つけたのか、急に電話がかかってきたのか──。その違いは数値上では判断できません。
つまり、データを見るだけでは、ユーザーを“理解したつもり”になってしまう危険があるのです。本来のUXデザインやマーケティングは、数字の裏にある「なぜ」を解くことに意味があるのではないでしょうか。
そのためには、定量データと定性データを行き来する姿勢が欠かせません。アンケート、ヒアリング、カスタマーサポートの声など、ユーザーの「生の声」を拾い直すこと。それが、データを“生かす”ための土台になります。
「活かす」とは、ユーザー理解に返すこと
データを取ることの目的は、ビジネスの効率化だけではありません。本来は「ユーザーの理解を深め、より良い体験を提供すること」にあります。たとえば、行動データから課題を見つけたなら、その裏にある“人の気持ち”を掘り下げて、次の体験設計に反映する。そこまでが、データ活用の一連の流れだと考えます。
数値の改善はあくまで副産物であり、目的ではありません。もしデータを取っても、活かされないまま眠っているなら、それは単なるコストです。ユーザーの行動を理解し、より良い体験に還元できるとき、はじめてデータは意味を持ちます。
関連記事:フィードバックがなくても、ユーザーは離れていく──“声なき離脱”と向き合うUX設計
データ時代の“ユーザーファースト”とは
データ活用が当たり前になるほど、「何を取るか」よりも「どう解釈し、どう使うか」が問われるようになります。
数値そのものが意思決定をしてくれるわけではありません。そこに意味づけを与え、体験の文脈に引き戻す作業があって、はじめて判断につながります。
数値を追うこと自体が悪いわけではありません。
ただ、数値で語れるものだけが議論の対象になった瞬間、UXは静かに後景に退いてしまいます。
UXを軽視しているのではなく、数値で語れないものが、判断の場からこぼれ落ちているのです。
外部から関わり、分析結果を翻訳する立場にいると、「この数字は何を示していて、何を示していないのか」を説明する役割を求められることがよくあります。
そのたびに感じるのは、データは結論ではなく、問いを立てるための材料にすぎないということです。
データを取ることは手段であり、目的ではありません。
数値を動かすことではなく、人の行動や気持ちを理解すること。
その理解を次の体験設計に返していくこと。
取るなら活かす。活かせないなら取らない。
データをユーザー理解に引き戻し続ける姿勢こそが、これからの時代における“ユーザーファースト”なのだと思います。