気づかれなければ、ないのと同じ──発見されるUIをつくるUX設計
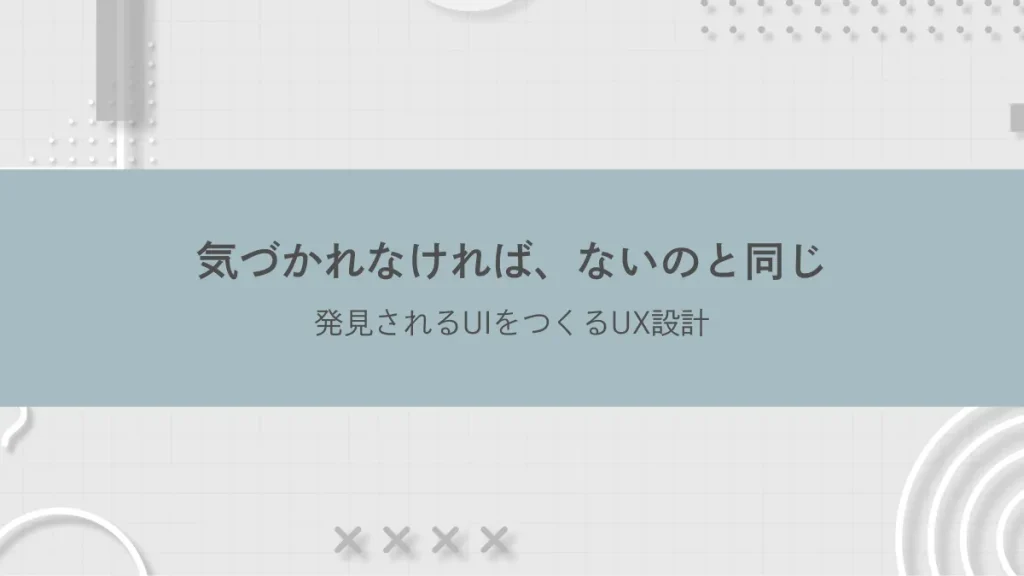
どれだけ丁寧に導線を設計しても、ユーザーがその存在に気づかなければ、意味はありません。
それが、UIにおける「発見可能性(Discoverability)」の問題です。
「ここにCTAを置いた」
「リンクもちゃんと設置している」
「説明文も書いてある」
設計している側としては、そう言いたくなる気持ちも分かります。
ただ、ユーザーの視界や意識に入っていないのであれば、それは存在していないのとほぼ同じです。
UXは体験であり、体験は「知覚」されて初めて成立します。
つまり、気づかれないUIは、設計ミスの一種だと考えたほうがいいのだと思います。
発見されないUIは「置いていない」のと変わらない
ユーザーは、設計者が期待するほど画面をじっくり見ていません。
実際のところ、多くのユーザーは、
- ざっくり眺めて
- 自分に関係ありそうな情報だけを拾い
- 目的を果たしたらすぐ離れる
という行動をしています。
そのため、ボタンやリンクが“物理的に存在している”だけでは足りません。
- 視界に入り
- 意味が瞬時に伝わり
- 「自分に関係がある」と認識される
この条件を満たして、初めて「存在している」と言えます。
「見える場所に置いたつもり」と「実際に見える場所にある」は、まったく別物です。
なぜユーザーは気づかないのか
情報が多すぎて、何も見えなくなる
1画面に要素を詰め込みすぎると、ユーザーの視線は分散します。
特にLPやサービス紹介ページで、
- バナー
- ボタン
- 画像
- 強調テキスト
が同時に主張していると、どれも印象に残らなくなります。
「全部大事だから全部載せる」という設計が、結果的に「何も伝わらないUI」を生んでしまうことは、現場でもよく起きています。
ユーザーの期待とズレている
ユーザーは、「ここにはこういうものがあるはず」という無意識の期待を持って画面を見ています。
- ログインは右上
- 次へ進むボタンは下部
- 購入ボタンは目立つ位置
こうしたWeb上の“慣れ”とズレた配置は、視界に入っていても、認識されないことがあります。
見えているのに、気づかれていない状態です。
デバイスや状況によって、見え方は変わる
PCでは分かりやすいUIでも、スマホでは気づきにくいことはよくあります。
- ホバー前提の表現
- モーダルの存在
- アコーディオンの開閉
また、
- 移動中に片手で操作している
- 急いで目的だけを済ませたい
こうした利用シーンでは、認知の精度自体が下がります。
発見可能性は、デバイスや文脈によって変わるものだ、という前提で考える必要があるように感じています。
「発見される」ための設計は、派手さとは別の話
発見可能性を高めるというと、「目立たせること」だと思われがちです。
でも、
- 派手なポップアップ
- 過剰なアニメーション
- 強すぎる色使い
これらは、不快感を生むリスクも同時に高めます。
発見されるUIとは、押しつけるUIではありません。
- 視線の流れに自然に置かれている
- 情報にリズムがある
- 重要な要素だけが、少しだけ前に出ている
ユーザーが「自分で気づいた」と感じられることが、もっとも信頼される体験につながります。
小さな反応が「ここは触れる」を教えてくれる
- ホバー時の色変化
- タップ後のちょっとした動き
- 開閉時の微細なアニメーション
こうしたマイクロインタラクションは、「ここは操作できる」というサインになります。
静的なUIよりも、ほんの少し反応があるUIのほうが、圧倒的に気づかれやすい。
これは、観察していると本当によく分かります。
最後に:発見されて、はじめてUXは始まる
ユーザーは、見ているようでほとんど見ていません。その事実を受け入れることが、UX設計のスタート地点だと思っています。
どれだけ考え抜かれたUIでも、気づかれなければ、存在しないのと同じ。発見されて、使われて、はじめて体験になる。
発見可能性は、UX設計の「前提」であり、「入り口」です。
見えないUXと向き合うために、まずは見えるUIをつくることから始めていきたいと感じる今日この頃です。